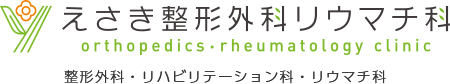成長期にスポーツに携わる子どもは「腰椎分離症」を引き起こす可能性があります。
腰椎分離症は疲労骨折の1種であり、腰痛と勘違いして見逃してしまう方もめずらしくありません。
悪化すると長期間スポーツを休まなければいけなくなる可能性もあるため、症状や原因をよく理解しておくのが重要です。
この記事では、成長期に起こりやすい「腰椎分離症」の原因や症状、治療法を解説します。
■腰椎分離症とは?
腰椎分離症とは、スポーツなどで腰の骨の脆い部分に負担がかかり、疲労骨折が起きている状態を指します。
腰の曲げ伸ばしが多いスポーツや、身体を捻る機会の多いスポーツをする子どもに多く見られるケガの一種であり、運動中の腰痛をきっかけに発覚するケースが多いです。
初期には腰痛しか感じない場合が多く、疲労骨折が起きていると気づかない方も珍しくありません。
腰痛が長引いていたり、痛みが強くなっていたりする場合、腰椎分離症が生じている可能性もあります。
悪化すると足のしびれや脱力感などが生じる可能性もあるため、早めに検査を受けることが大切です。
■腰椎分離症の原因
腰椎分離症が起きる主な原因は、身体を強く反らしたり捻ったりしたときに、背骨に強い負担がかかることです。
特に、野球やバレーボール、サッカーやバスケットボールなど身体を捻る機会が多いスポーツや、柔道、ウェイトリフティングなど背骨に負荷がかかるスポーツで多く見られます。
腰椎分離症が成長期の子どもに多いのは、骨の成長が未熟でやわらかいことが理由です。
成長期は身体もやわらかく、過度に腰を反らしたり捻ったりする場合もあるため、骨に負担がかかり、疲労骨折が起きてしまいます。
■腰椎分離症の症状
腰椎分離症の主な症状は「腰痛」です。
初期のうちは運動時にのみ痛みを感じ、特に腰を反らしたり捻ったりしたときに痛みを訴える場合があります。
悪化すると痛みが強くなり、日常生活の中でも痛みを感じるようになるケースもあります。
また、稀に下半身のしびれや痛みを感じる方もいるため、腰椎椎間板ヘルニアや坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)などとの判別が必要です。
■腰椎分離症の治療法
腰椎分離症の治療法には、主に以下の2種類があります。
-
・保存療法
-
・手術
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◎保存療法
保存療法は、手術を行わずに骨がくっつくのを待つ治療法です。
保存療法で優先されるのが腰の「安静」であり、激しい運動や、強く身体を反らせたり捻ったりする動きを制限し、骨がくっつくのを待ちます。
保存療法の最中は運動を一旦中止することがありますが、リハビリでストレッチを実施したり、専門家の監督のもと背骨に負担のかからないトレーニングを実施したりし、身体機能を維持します。
リハビリで正しい筋肉の使い方を身に付けたり、体中の筋力のバランスを調整したりすることで、復帰後の再発防止やパフォーマンスの向上を目指すことも可能です。
また、痛みから日常生活に支障が出ている場合はコルセットを使用し、身体の動きをサポートすることもあります。
保存療法にかかる期間は骨の状態や痛みの程度に寄りますが、短くても1~3ヶ月、長くて半年~1年程度はかかる可能性があることを覚えておきましょう。
◎手術
保存療法で痛みに変化が見られない場合、手術を検討する場合もあります。
発症から時間が経つと、骨が自然にくっつかなくなり、痛みやしびれなどが持続する場合があるため、金属で骨をつなぐ必要があるのです。
手術になった場合、およそ2週間~1ヶ月程度で退院できます。
ただし、手術の方法や術前の症状の程度、術後のリハビリの進捗次第でスポーツ復帰までの期間は異なるため、復帰するタイミングは医師や理学療法士とよく相談することが大切です。
■腰椎分離症を運動しながら治すことはできる?
検査で腰椎分離症が発覚した場合、可能であれば運動を中止し、治療に専念することをおすすめします。
骨に負担をかけ続けると治りが遅くなるだけでなく、骨折した部位がずれてしまい、自然に治らなくなってしまう可能性があるためです。
どうしても運動しながら治したい場合、医師や理学療法士と相談して運動量を調節しましょう。
身体の使い方についてアドバイスを受けたり、腰に負担のかかる動きをチェックしたりなどして、悪化を予防しながら運動する方法を理解するのが重要です。
■腰椎分離症かな?と思ったら早めに整形外科へお越しください
腰椎分離症は、成長期のスポーツに携わる子どもに多いケガの1つです。
悪化を防止し、痛みをコントロールして運動に復帰するには、専門家による検査と治療を受けることをおすすめします。
『えさき整形外科リウマチ科』では、患者様の希望を考慮しながら、腰椎分離症の治療や、運動に関するアドバイスを実施しています。
興味のある方は、お気軽に当院へお越しください。